-
「たぬたぬさんとバスレフダクト」の続きです。
|
 久々にスピーカーをいじってみました。 久々にスピーカーをいじってみました。音については大体満足していて、一時期のオーディオ中毒みたいな状態は脱しているのですが、そうなって来るとスピーカーをもう少し目立たなくしたいと思えて来ました。 ユニットの黒くて大きな丸というのは意外と目立つのです。 先の尖ったフェイズプラグなんかが付いていると、巨大な目にも似てくるせいか、さらに視覚的な圧迫感が増すように感じています。 というわけで布でカバーを付けてみました。 材質はダブルガーゼというガーゼ状の布を二枚貼り合わせた物。これを一枚にはがして使っています。 ユニットが透けて見えるくらいの薄さなので、音への影響は最小限にできているんじゃないかと思います。 このあたりもこだわり出すと……枠の形はどうするか、素材の布は伸びるタイプかぴんと張るタイプか、天然素材か化学繊維か……などなど、色々と考えることが出て来て面倒なことになりそうです。 ツイーターだけでも露出して使えると音はだいぶ違うのですが、見た目が悪くなってしまいますね。 |
 メインのかめさんスピーカーの方はこんな感じです。 メインのかめさんスピーカーの方はこんな感じです。木のような色で、薄い素材というのがなかなか見つからなかったので、あずき色で我慢しています。 やはり音は劣化した感じになるので、良い音で聞きたい時はツイーターの布だけはめくって使うことにしました。サブの方も同じ感じでめくって使おうかと思います。 |
 前回はユニットが目立たないように目隠しを付けたのですが、音についてももう少し割り切ったセッティングにしてやることにしました。 前回はユニットが目立たないように目隠しを付けたのですが、音についてももう少し割り切ったセッティングにしてやることにしました。というわけで、バスレフはやめて完全に密閉型にして使うことにしました。 以前のような紙張りではなく、しっかりと板で塞いであります。 スピーカーの置き場所、部屋の広さ、聴く場所、全ての条件が悪いので、バスレフだとどうしてもぼわぼわした音になりやすいようです。 さらにアニソンみたいな、声優さんが4人くらいで合唱していて、そのうしろでドラムがものすごい早さで連打されていて、ぱっと聴いただけでは気付かないようなメロディーが隠しキャラのように埋め込まれているような曲をかけたりすると、ごちゃごちゃとわけがわからない音になってしまって、とてもBGMにして作業できるような状態ではなくなってしまうのです。 でもこれですっきりキレの良い音になって、低音もかえって聞き取りやすいくらいになってくれたと思います。 ただ、このPARCのユニットはセンターキャップが付いていないので完全な密閉とは言えず、まだ少しバスレフ臭さは残っている気はしています。 あとは密閉で少し詰まった音になった分、ネットワークで中域を少し持ち上げてやりました。 正確には持ち上げたのではなく、元々下げてあったものをユニット本来のあたりまで戻したということです。 それからさらに微調整として、振動板に接着剤を塗りつけて重りと補強にしておきました。 効果はあるけど見た目が悪くなるので以前はボツにしていた、バッフル面の吸音材も復活させてあります。 あとは音を聞きながらツイーターのバランスを整えて、密閉型でもそこそこの低音感は得られるように出来たと思います。 というわけで一応は満足していたのですが、サブのDENON SC-CX101も同じように密閉にしてやったところ、メイン以上の化け方をして、キレキレの良い音になってしまいました。 センターキャップ付きなので、こちらの方が密閉向きだったようです。 さらに振動板が二重構造になっているので振動板を通した箱の音漏れも少なく、吸音材がゼロでも問題なく使える点も効いていると思います。 それからノーマル状態での低音の出方からして、ユニットのQが高くて元々密閉向きの特性だったんじゃないでしょうか。 PARCのアルミコーンはQが低くて、ちょっと密閉だときつかったかも知れません。 ウッドコーンの13cmなら密閉でも行けそうですが、フェイズプラグからの空気漏れがあるのでやはり密閉は難しそうですね。 そんなわけで、なかなかサブに勝てないもやもや感はあるものの、単体の変更前後で比べるなら前より良い音になっているんじゃないかと思います。 |
 メインのかめさんスピーカーはやはり容積が大きすぎた感じなので、中に板切れを入れて、1Lくらい小さくなるようにしてみました。 メインのかめさんスピーカーはやはり容積が大きすぎた感じなので、中に板切れを入れて、1Lくらい小さくなるようにしてみました。木工ボンドと木ねじでしっかり貼り付けてあるので、箱の強度も上がって音にも良いと思います。 箱の内面にデコボコができて響き方も変わったようなので、吸音材も以前の60%くらいまで減らせるようになりました。 これで少しは音が良くなっているはずなのですが、耳で聞いた感じでは劇的な変化という程ではなかったです。 シミュレーションしてみても、1Lくらいではそんなに違いは無いようでした。 |
 せっかく密閉型にしても、フェイズプラグの隙間から空気が漏れていると無限大BOXに近付いてしまうわけで、そうすると空気ばねが緩くなって、100〜300Hzの大事な部分が出づらくなってしまう……のではないか? せっかく密閉型にしても、フェイズプラグの隙間から空気が漏れていると無限大BOXに近付いてしまうわけで、そうすると空気ばねが緩くなって、100〜300Hzの大事な部分が出づらくなってしまう……のではないか?というわけで、フェイズプラグを取り外して自作のセンターキャップを付けてみました。 フェイズプラグはしっかりと接着されていたのですが、金槌で横から叩いてやると、ぽきっと根本の部分が折れて、案外簡単に外すことが出来ました。 |
 センターキャップはやや厚めの紙を円すい状に加工して、表面を接着剤でコーティングしたものです。 センターキャップはやや厚めの紙を円すい状に加工して、表面を接着剤でコーティングしたものです。さらに本格的にやるなら、ボイスコイルボビンに穴を空けたりして、内側に空気を逃がしてやる必要がありそうですが、さすがにそこまではやっていません。 音の方は問題の100〜300Hzは期待した程の変化は無かったものの、密閉らしい引き締まった低音になって、非常に良い感じになってくれました。 センターキャップによる重量増加や、センターキャップ自身が出す音の影響が心配だったのですが、それほど悪影響にはならなかったようです。 |
 前々回にネットワークの変更をした時にちょっとやりすぎていたようで、3kHz付近の歪みっぽさが復活していたので、またネットワークをいじってみました。 前々回にネットワークの変更をした時にちょっとやりすぎていたようで、3kHz付近の歪みっぽさが復活していたので、またネットワークをいじってみました。しかし3kHzを下げると元気の無いつまらない音になるし、上げすぎると歪みっぽさが出てしまう。手持ちの定数ではぴったりの調整は出来そうもない……というわけで思案した結果、ネットワークは変えずにウーハー用の目隠し布の厚みで調整してやることにしました。 今まではガーゼ1枚分だったところを2枚に増量。これで3kHzから上のうるさく感じやすい帯域が減って、歪みっぽさが少しだけ取れてくれたようです。 さらに、布が厚くなったこととセンターキャップが付いたことで、箱の中の音が漏れにくくなっているはずなので、吸音材ももっと減らして完全にゼロにしてしまいました。 写真の白い布切れが今回取り出した吸音材ですが、これだけの量で低音の締まり具合などが全然違うのです。 ネットの作例を見ていると吸音材の入れ方は千差万別で、私みたいにゼロにしてしまう人もいれば、反対に箱いっぱいに充填する人もいるみたいです。 私の場合は一般に言われる定在波はあまり気にしていなくて、尾を引くような反響音が取れるぎりぎりの量を入れるようにしています。 やり方としては、箱を最後まで組み上げて音を鳴らすのと同じ状態にしておいてから……箱をげんこつで叩く。 それで「ほわーん」と尾を引くような音がしたら、それが無くなるまで吸音材を増やしていく、という方法です。 完全に無くなるちょっと手前で止めておくと、女性ボーカルに適度な味付けが出来るんじゃないかと思います。 定在波の考え方だと、私も含めて素人にはどの音がそれなのか分かりづらくて、ついつい闇雲に入れすぎてしまいがちなんじゃないでしょうか。 |
 しかしちょっとだけ吸音材を戻そうか迷ってしまいました。 しかしちょっとだけ吸音材を戻そうか迷ってしまいました。でも少しでも吸音材を入れるとぼわぼわした気持ち悪い音になってしまいます。 というわけで今度は吸音材の代わりに円柱状の木材を入れてやることにしました。ニスなどは塗らずに、あえてケバ立った表面のままで使います。 これを天地方向に突っ張り棒のような感じで入れてやって、板の補強と音の拡散をさせてやろうという狙いがあります。 結果、箱の反響音は前回少量の吸音材を入れていたのと同等に。低音の締まり具合は吸音材ゼロならではのものに出来たんじゃないかと思います。 というわけで、かめさんスピーカーのセッティングが完了しました。 100〜300Hzは相変わらず出ていなくて、そこから来る不満も無いではないですが、低音感みたいなものは出ているし、キレが良くて楽しく聞ける音になっているので、これはこれでありなんじゃないかと思います。 サブのスピーカーと比べても、どちらも一長一短かな……というくらいまではなんとか持って来れたようです。 |
 適当に改造したサブスピーカーの音があんまり良いもので、高いアンプをつないでやったらもっと良くなるんじゃないか……ということで、試しにメイン用のアンプをつないでみました。 適当に改造したサブスピーカーの音があんまり良いもので、高いアンプをつないでやったらもっと良くなるんじゃないか……ということで、試しにメイン用のアンプをつないでみました。しかし出て来た音はもったりした元気の無い音でがっかり。安いアンプの方が断然音が良いです。 高くて出力が大きく、重たいアンプは、音も重たくなってしまうのか? どうやらかめさんスピーカーの音に元気が無かったのは、アンプのせいでもあったようなので、このアンプまわりも少しいじってやることにしました。 まずスピーカーケーブルをぎりぎりまで細く、0.3sqの物に交換。 さらにアンプの足の下に竹ひごをはさんで、土台と点で接触するようにしておきました。 まるで科学的でないオカルトじみた話であれなんですが……今まで眠たくなってしまうような音だったのが、くっきりはっきり元気の良い、ノリの良い方向に変わってくれたように思います。 たぶんf特は全然変わっていなくて、気のせいかなーという程度の差なのですが、眠くなるか元気になるか……みたいな違いがある気がしています。 それからスピーカーの吸音材も、やっぱり少し入れた方が良い感じだったので入れることにしました。 音楽を聴くなら入れなくても良さそうですが、WebラジオなどでBGMの無い、声だけの状態で鳴っていると、箱の中の反響音が聞こえてしまうのです。 というわけで少しだけ……今度はタオルの切れ端からさらに薄くして、例のダブルガーゼを一枚にはがした物を使うことにしました。大きさは7×14cm。これで反響音はほぼ聞こえなくできました。 |
 3kHz付近の歪みっぽさをもっとしっかり取りたいので、振動板へのコーティングを増量することにしました。 3kHz付近の歪みっぽさをもっとしっかり取りたいので、振動板へのコーティングを増量することにしました。今まではフチの部分だけだったのを、全体をしっかりカバーするように塗りつけておきました。素材はセメダインです。 今まで振動板は少しでも軽い方が良いと思っていたし、ブチルゴムを貼り付けた時に音が鈍くなるのも確認していたのですが、センターキャップを付けたり接着剤を塗りつけたりした結果、考えが少し変わって来ました。 材質によるのではないか? ゴムのようなやわらかいものでなければ、はっきりわかるような悪影響は無いんじゃないかと思い始めています。 ……実際はどうなんでしょうね。 しかし肝心の歪み感に対する効果は、あまり無かったようです。 アルミコーンなので、振動板の強度はもともと十分だったみたいですね。 とすると幅広のゴムエッジあたりを疑いたくなって来ますが、これはさすがに接着剤で固めてしまうわけにはいきません。難しいところです。 |
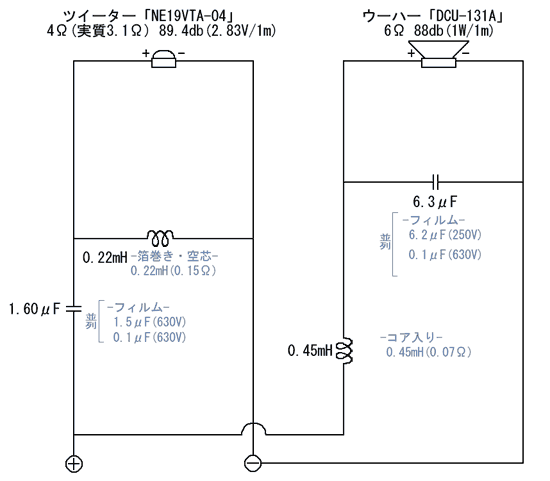 ネットワークは最終的にこんな感じになりました。 コイルはシンプルにひとつのみ。 小容量で耐圧の高いコンデンサを並列に入れているのは、おまじない程度ですが、その方がなんとなく音が良いと感じたからです。 あとは以前やっていた素子の固定方法も、今回は徹底しておきました。 爪楊枝などを利用して土台から浮かせて設置すると、シャープでキレの良い方向に変化する……ように感じています。 ツイーター本体もゴムと両面テープで固定していたのを、堅めのブロックで浮かせて設置するようにしました。 かなりはっきりした変化がある(ように感じた)ので、ツイーターにかぶせた布もわざわざめくらないで使うことにしました。 |
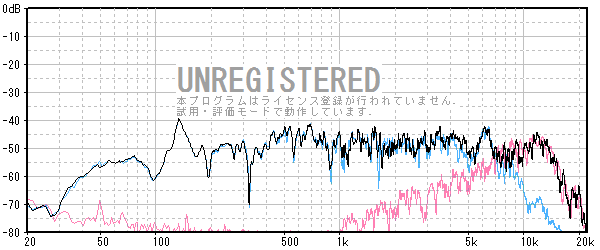 そろそろ完成かな……という感じになって来たので、確認のためにf特を測ってみました。 センターキャップを付けたり振動板をコーティングしたりしたので、特性もだいぶ変わっただろうと思ったのですが、相変わらずのアルミコーンでした。6.5kHzあたりのピークは、ほぼそのまま残っていますね。 その他、色々とオカルト的なおまじないをほどこして、聴感では変わったと思っていた部分も、グラフにはあまり現れてないみたいでした。 音のキレというか、解像度というか、眠くなるか楽しくなるか……みたいな差なのですが。 このあたりも人によってそれぞれで、徹底的に測定を気にする人もいれば全く気にしない人もいるみたいです。 その中間という人が一番多いのでしょうか。 私も自分では中間派だと思っているのですが、最後の微調整の時などは、面倒なので測定せずに耳だけで決めてしまうことが多くなって来ました。 |
 全体の設置状況はこんな感じです。 全体の設置状況はこんな感じです。布をかぶせて使うことにしたので、今回はユニットの外観が変わるような改造も思い切って行いました。 二度と元に戻せないような状態になってしまいましたが、結果としては成功だったと思います。 やっぱり良くも悪くも現代的な、わーわーごちゃごちゃピコピコした曲には、空気バネでしっかり制動をかけた密閉型の方が合うんじゃないかという気がしますね。 矩形波のエッジが見えてくるような解像度が求められているのかも知れません。 Qの高いユニットを小さい箱に入れて100〜300Hzをしっかり出す。そうするともっとコンパクトに(自分にとって)良い音のスピーカーが作れるんじゃないかな〜なんて夢が膨らみます。 メーカーが作らないような、バックロードホーンみたいなスピーカーが自作の醍醐味という意見もありますが、ラジカセみたいな物を除くと実は密閉型もメーカーではあまり作られていません。 ある意味自作ならではの音と言えるのではないでしょうか。 密閉型の音は良いですよ〜。 |
だいたい良い感じの音になっていると思いますが、またどこか気になったらいじるかも知れません。 気が変わって、バスレフに戻ってしまう可能性もあると思います。 |
