-
「かめさんスピーカー2012・その2」の続きです。
|
 f特を測ってみたところ、100Hzあたりに大きな山ができて、そこから下は急降下という特性になっていました。 f特を測ってみたところ、100Hzあたりに大きな山ができて、そこから下は急降下という特性になっていました。どうやら紙を貼ってあるだけだと、バスレフ型としての動作が残ってしまうようです。 直径8cm・長さ2cmの板厚分の穴なので、バスレフとしての動作も相当高めに出てしまっていました。 ダクトにスポンジなんかを詰めたりするダンプドバスレフと似たようなものだったのかも知れませんね。スポンジが紙に代わっただけという…… というわけで厚紙で紙筒を作って、50hzくらいまでバスレフの共振が下がるように調整しておきました。 その上からまた薄い紙でフタをして完成です。 薄い紙の補強の仕方も少し変えておきました。今回は「短めの十の字補強」です。 ダクトの材質は今までだと、厚く硬く、さらにゴムを巻いたりして徹底的に鳴き止めをする方向でしたが、これも最近凝っている方向に変えて、薄く軽く鳴きやすいようにただの厚紙にしておきました。 音の方はフタをしない方が開放的で良いのですが、長時間聞いているとやはりバスレフ臭さが気になってしまうので、フタはすることにしました。 |
 ボリュームを上げると薄い紙がびりびりと鳴ってしまうのが気になったので、なんとかしてみようと思います。 ボリュームを上げると薄い紙がびりびりと鳴ってしまうのが気になったので、なんとかしてみようと思います。まずはエージングして紙が馴染むのを待ってみたのですが、それもダメ。 この方式をダンプドバスレフの一種と考えると、ダクトから出入りしようとする空気が激しく薄い紙を叩いていることになるので、それなりの制震をしてやらないといけないようです。 というわけで写真のように全体にマスキングテープを貼ってみました。 このマスキングテープは長時間貼っていても、のりが固まりづらいので振動を吸収するのに調度良いと思います。 ゴムシートなんかも考えたのですが、重たくなりすぎてせっかくの薄い紙の良さが消えてしまいそうなので、やめておきました。 それから直径1cmくらいの小穴を開けて、ダクトから叩きつける空気を少し逃がしてやることにしました。 これでかなりボリュームを上げても、以前ほどびりびり音は鳴らなくなったようです。 |
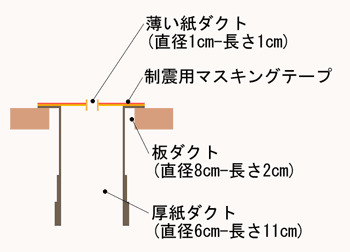 小穴は圧力を逃がすだけじゃなくて、ダクト状にしてバスレフダクトとしても動作するようにしておきました。 小穴は圧力を逃がすだけじゃなくて、ダクト状にしてバスレフダクトとしても動作するようにしておきました。断面図は左のようになります。 3種類のダクトと密閉型が合わさったような構造にして、共振を分散できたら良いかなという狙いがあります。 解説すると…… まずは最も頑丈な板のダクト。ダクトの周辺には厚紙や薄い紙が色々くっついていますが、板の厚さには遠く及ばないので、全て無視して考えたとすると100Hzくらいにピークが出るバスレフということになります。 次に厚紙ダクト。これは50Hzくらいにピークが出る計算です。出口に薄い紙が貼られているので力は弱まるものの、それなりに低音を増強してくれると思います。 そして薄い紙のダクト。設定は25〜30Hzくらい。これくらい小さいとたいした効果は無いかも知れませんが、他のダクトと違ってフタをする物が無いのが強味でしょうか。 最後に密閉型としての性格も少し持っていると思われます。 ……という仮説なのですが、実際はどうなるでしょう。測定してみました。 |
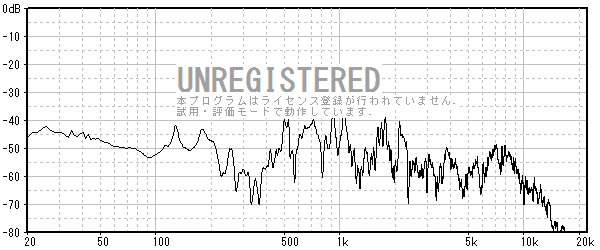 ダクトの出口から3cmくらいの距離で測定したグラフです。 ユニットの前面からの音もマイクが拾っているので、どう読み取ったらいいか迷うグラフですが、とりあえず20〜300Hzあたりがダクトの音と考えると……、普通のバスレフのように鋭い山にならずに、共振分散の効果はしっかり出ているように見えます。 その代わり全体的に山が低くなってしまっているので、低音増強の効率は悪いみたいです。 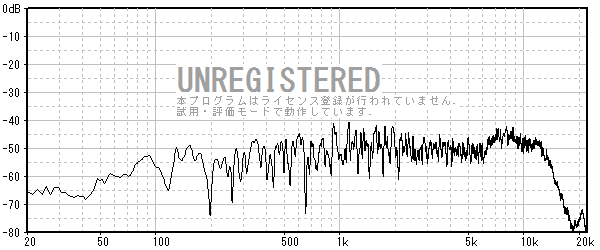 150cmくらい離れた普段の視聴位置で測定したグラフです。 やはり普通のバスレフのように50Hzまでフラットというわけにはいかないですね。グラフとしては少し物足りない感じでしょうか。 しかし100〜200Hzあたりの中抜けが抑えられているし、バスレフのように50Hzあたりからすぱっと音が無くなったりせずに、緩やかに低い周波数まで音が出続けるのは良いところだと思います。 聴感でもこっちの方が、低音の質感が良いように感じました。 これを見ると小穴のサイズをもう一回り大きくしてもいいのかな〜という感じもしますが、13cmのウーハーなのでこんなものかな〜という気もするので、しばらくはこの設定で音楽を楽しみたいと思います。 |
|
やっぱりダクトを大きくすることにしました。 とりあえずダクトを長めに作っておいてから、測定を繰り返しながら少しずつ切り詰めて調整して行きました。 頑丈な塩ビパイプなどと違って、気軽にカットアンドトライできるのが良いですね。 結果、直径1cm-長さ1cmだったダクトが、直径2cm-長さ2.3cmになりました。 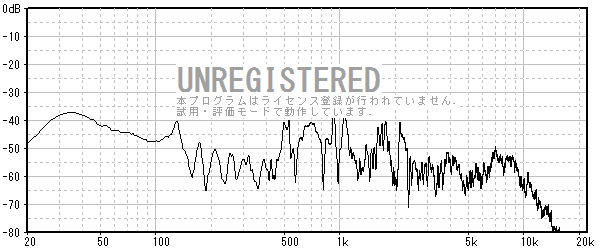 (↑カーソルを乗せると、比較用にひとつ前のグラフが表示されます) ダクトの出口から3cmくらいの距離で測定したグラフです。 ダクトを大きくしたので、30〜100Hzあたりの山が大きくなりました。 200Hz付近ががくっと下がっているのは、空気の逃げ道ができたせいで板厚ダクトの効きが悪くなったからでしょうか? 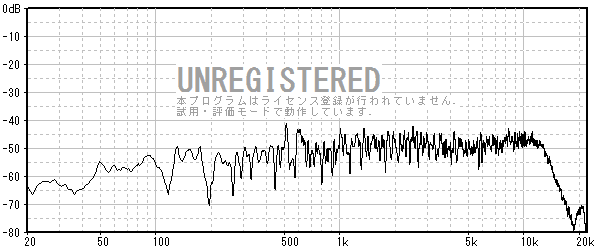 (↑カーソルを乗せると、比較用にひとつ前のグラフが表示されます) 150cmくらい離れた普段の視聴位置で測定したグラフです。 これくらいのバランスだとグラフ的にも満足ですね。 音については大体グラフの通りで、前よりちょっと低音がよく出るようになった感じです。 低音のレンジが広くてカーブも自然なので、ベースの音階なんかが聞き取りやすくなった気はします。 普通のバスレフでバランスが取れていない時などは、ベースの音量が上がったり下がったりして不自然になりやすいのです。 ただ密閉状態と比べるとバスレフくさい音の緩さが目立って来たので、以前試した穴あき厚紙パッキンを復活させたり、ツイーターまわりの浮かせ方を変えたりして、解像度が高くなるように微調整しておきました。 |
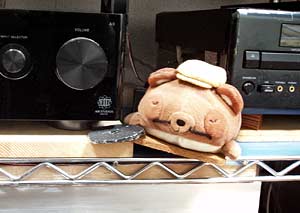 解像度アップの方向にシフトして来ると、アンプでもう少し良くなるんじゃないかと思えてきました。 解像度アップの方向にシフトして来ると、アンプでもう少し良くなるんじゃないかと思えてきました。ミニコンポで試したような方法が、高いアンプでも使えるんじゃないか? そうは言っても音質最優先で設計されているはずの高いアンプは、下手にいじるとかえって音を悪くしそうです。 とりあえず外側から眺めてみると……、ケースは頑丈に作られていて叩いても変な響き方をしないので問題無さそう。わざわざフタを外して故障の原因にもしたくないです。 それからインシュレーターは、しっかりした金属製で申し分なし。 ただ、インシュレーターの下に柔らかいフェルトのような素材が張り付いていたのが、ちょっと気になりました。 これは機械がぐらぐらして良くないんじゃないか? まぁ、これくらいならということで、試しに剥がしてみました。 すると……見違えるようにくっきり元気な音になってしまいました。 ミニコンポで足回りをいじった時と同じ傾向ですね。 メーカーとしては音がきつくなるのを防ぐためにわざと貼っていたのかなーという気もしますが、剥がした方が好みの音なのでこれは剥がして使うことにしました。 あとはラックに傷を付けないためだとか、4点支持だと微妙な誤差でがたつきが出やすいなど、ベストな音とは別の理由で貼っていたのかもしれません。 それにしてもアンプの足回りは予想以上に効きますね。 アンプの性能なんて回路で決まるものであって、インシュレーターでどうこうなんてのはオカルトだと思っていました。 いやもう、私もはたから見たら完全にオカルト世界の住人かも知れませんねー。 |
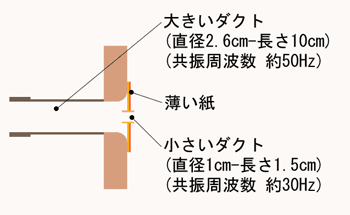 サブスピーカーを少しいじってみました。 サブスピーカーを少しいじってみました。変更点は薄い紙で密閉していたダクトをメインと同じ方式にすることです。 元の穴が小さいので、ダクトは三段階ではなく二段階にしました。 こっちの方がすっきりまとまっていると思います。 f特は測定してないのですが、メインと同じく低域のレンジが下まで延びたように感じました。 |
 あとはアンプの足回りを木のブロックから、以前スピーカー用に使っていた「つまようじ6段重ねインシュレーター」に変えておきました。 あとはアンプの足回りを木のブロックから、以前スピーカー用に使っていた「つまようじ6段重ねインシュレーター」に変えておきました。これで低域のレンジを延ばしつつ、ぼわつかずにしっかりと駆動できるようになったと思います。 メインのスピーカーと聴き比べてみても、引けを取らないどころか多くの部分で勝っているんじゃないかという感想になってしまいました。 箱が小さいせいなのか低音が引き締まっていて、ごりごりと気持ちいい解像感があること。 ウーハーにネットワークが入っていないので、微少な音までしっかりと出してくれること。 それからほぼフルレンジのせいか、3kHzあたりのうるさくなりがちなところが、メインと比べて自然な出方になっていると感じました。 以前からかめさんスピーカーの方は3kHzあたりがうるさいうるさいと言っていて、色々対策してきたのですが、これと比べるとまだ少し取り切れていなかったと感じてしまいます。 こっちはこっちでグラスファイバーの強烈なピークがありますが、6〜9kHzの高めに出ているせいなのか、無視して使っても不思議と耳につかないです。 ダメなところはツイーターがいかにも安物で、フルレンジの補助的な使い方しか出来ないところ。 それとユニットを箱に接着してしまったことは、すごく後悔しています。 厚紙パッキンで浮かして取り付けた方が音が良くなる気がするのです。 サブと割り切りすぎて、取り返しの付かない方法まで大胆にやりすぎてしまいました。 |
 サブスピーカーを乗せている棚を改造してみました。 サブスピーカーを乗せている棚を改造してみました。柱の部分がプラスチックの中空パイプだったので、しっかりとした木製の柱にしておきました。表面はニスでかちかちに固めてあります。 今まではスピーカーの音に合わせて、プラスチックの柱がぽこぽこと鳴っていたのです。 中にボロキレなんかをきつく詰め込んでみても駄目。 水を入れたペットボトルを叩いてみるとわかると思いますが、外側が柔らかい物は中に何を入れても駄目なようです。 新しい木製の柱の方はそんなことはなく音も良いのですが、大音量の時に手を当ててみると、ぐぐっと揺すられるような感触はまだあるみたいでした。でも気にしないで使うことにします。 |
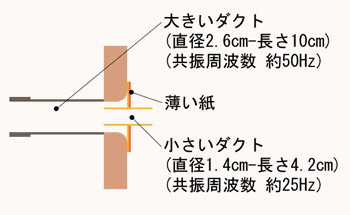 小さいダクトをひと回り大きくしてみました。 小さいダクトをひと回り大きくしてみました。小さいダクトの直径が大きくなったので、大きいダクトと薄い紙にかかる圧が弱くなっているはずで、50Hz付近の低音の暑苦しさが弱まったと思います。その分、小さいダクトの効きが強くなりました。 これで「小さいダクト→大きいダクト→ウーハー」の順でバランス良く低音が繋がったと思います。 今までは「ぼわぼわと不快にならないように」というのが低音のテーマだったのですが、ここへ来てようやく、気持ち良くノリノリになれる低音になってきた感じがします。 低音をプラスの方向で感じられるようになると、音楽の見え方が断然違って来ますね。 これはウーハーをスルーで使えているのも大きいと思いますが、自己流の二段階ダクトも結構効いていると思います。 名付けて、ダクトinダクト方式! ……とでもしておきましょうか。 |
|
最後のまとめとしてメインとサブのスピーカーの特性を測り直してみました。 ↓メイン - かめさんスピーカー (Lchのみ、150cmくらい離れた普段の視聴位置で測定) 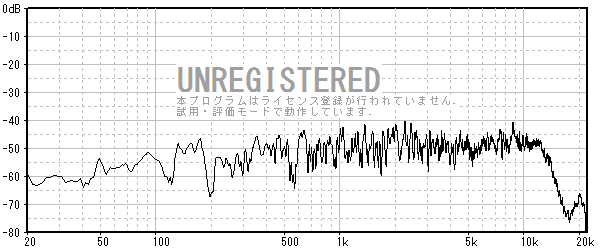 ↓サブ - DENON SC-CX101改 (Lchのみ、150cmくらい離れた普段の視聴位置で測定) 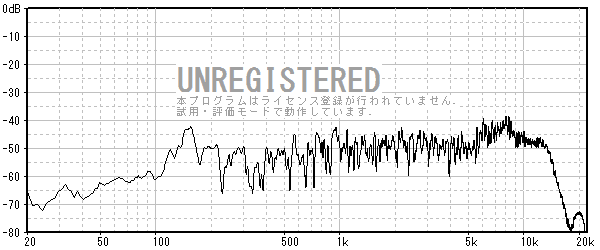 13kHzから上が、がくっと下がっているのはマイクが原因です。 そこを抜かして見ると、どちらもなかなか良い特性ではないでしょうか。 でも聴感ではサブスピーカーの方が低音が力強く出ているので、この結果はちょっと意外でした。 かめさんスピーカーの方は少しぼけ気味で、音がふわっと広がる感じ。これはLとRの距離が1.5mくらいで、かなり広くなっているせいかも知れません。 しかしこの特性からすると、かめさんスピーカーには聴感でも圧勝してもらわないと困りますね〜。 他に考えられる理由としては、やっぱりウーハーのネットワークでしょうか。かめさんスピーカーはコイルが2個入っているので、抵抗成分が0.2Ωくらい違うはずです。 |
 というわけでコイルを新しくすることにしたのですが、コイルが届くまでの間にダクト周りの設定を見直しておこうと思います。 というわけでコイルを新しくすることにしたのですが、コイルが届くまでの間にダクト周りの設定を見直しておこうと思います。まずは吸音材。 今回の目標はDENONのサブスピーカーなので、それに習って吸音材は全部抜いてしまいました。 やっぱりこの方が低音のキレは良くなるみたいです。 ただ気になる響きは復活してしまうことになります。 これは大きな板の真ん中辺りが、特定の周波数でびりっと震える時に出ている感じなので、本来は補強を入れた方が良いのかもしれません。 しかし今からでは無理なので、板表面の響きをやわらかくする目的で、響くところにやわらか目のマスキングテープを貼っておきました。 DENONのスピーカーでは分厚いゴムが板の真ん中に貼ってあったのですが、その意味がようやくわかった気がします。 |
 円形断面のダクトだとクセがつきやすいらしいので、多角形のダクトにしてみました。 円形断面のダクトだとクセがつきやすいらしいので、多角形のダクトにしてみました。太い方は八角形、細い方は六角形です。 それから紙がばたばた言うのを完全に無くしたいので色々試してみました。 表面を覆うテープをマスキングテープからビニールテープに変えたり、四隅だけビニールテープにしたり、ビニールテープそのものでフタを作ったりしました。 しかしばたばたが収まると低音の量も質感も悪くなってしまうのでした。 どうやら適度にばたばた言っているのが、低音のキレが良くなったと錯覚させていたみたいです。 「ぼーーーーー……」というダクトの音が、「ばばばばばば……」になる感じです。 サブスピーカーではそれくらいの方が楽しくて良いのですが、メインはやっぱり正攻法で行きたいですね。 |
 色々試しているうちに、だんだんわけが分からなくなって来て、最終的にはこんな形になりました。 色々試しているうちに、だんだんわけが分からなくなって来て、最終的にはこんな形になりました。上向きのダクトを前に向ければ、音が散らなくて良いんじゃないか? そのままだと開口が広すぎるので、色々な物を入れたり抜いたり、半挿しにしたり……などなど。 |
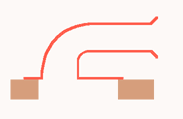 断面図はこんな感じになります。 断面図はこんな感じになります。今回は比較的普通のバスレフですが、板の厚味の影響が少しあるかも知れません。 |
 Rchは部屋の条件が悪くて低音が出過ぎになってしまうので、半分くらいフタをして低音が出すぎないようにしておきました。 Rchは部屋の条件が悪くて低音が出過ぎになってしまうので、半分くらいフタをして低音が出すぎないようにしておきました。 |
 コイルが届きました。 コイルが届きました。Jantzenの鉄芯入りコイルです。 数値は0.45mHで、貼ってあるシールによると抵抗は0.07Ωです。 今までのコイルは二つ合わせて0.19Ωだったので、0.12Ωも少なくなりました。 しかし今までと同じ0.49mHという数値は無かったので、他のパーツで微調整してやることにして、ツイーター用の抵抗とコンデンサも買っておきました。 抵抗は一度試してみたかった無誘導巻線抵抗です。 さて、どんな音が出るでしょう? |
 組み込みが終わりました。 組み込みが終わりました。今回は一度全部ばらしてから、ハンダ付けも丁寧にやり直してみました。 マイナス側の全ての線が合流する部分なんかは、山盛りのハンダでひどかったのです。そういった部分は圧着用のリングをはめて、ひとまとめに締め付けておきました。 それから真鍮釘に素子を留める方式は、便利なんですが余計な接点が増えるので止めにしました。 |
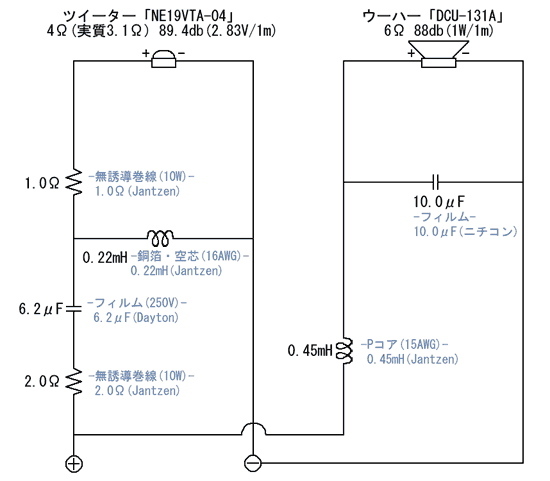 (↑カーソルを乗せると、比較用にひとつ前の状態が表示されます) 回路図はこんな感じになります。 ウーハーのコイル変更に合わせて、クロスオーバー周波数が高めへと少しずれました。 それからツイーターの方も抵抗が少ない方が良いだろうということで、合計3.7Ω使っていたものが3.0Ωで済むようにしてあります。これでニチコン以外は全てオーディオ用部品になりました。 さて、音出ししてみた感想ですが、だいぶ良くなったと思います。 前回書いていた音がぼけ気味という部分は、ほとんど解消できました。 しかしいっぺんに色々いじりすぎて、どの部分が効果的だったかまではわからなくなってしまいました。 たぶんハンダ付けをやり直したのと、箱の吸音材あたりが一番効いているんじゃないでしょうか。 それからDENONのサブスピーカーを目標に、力強くキレのある低音を目指して来たわけですが、それはどうやら失敗に終わってしまったようです。 こっちはこっちでクリアーで高解像度でワイドレンジな良さがあって、サブよりも高級な音になっているとは思うのですが、荒々しさが足りなくてちょっと物足りなかったりします。 これは、さわやかで空気のような……が売りのPARC Audioのユニットによるものか、そうでなければあとは箱の容積くらいしか考えられないですね。 まぁどちらも悪い音ではないので、スピーカー毎のいろいろな個性を楽しむことにしましょう。 |
 DENONのスピーカーとの違いをもう少し分析してみました。 DENONのスピーカーとの違いをもう少し分析してみました。音を出しながら箱を手で触れてみると、DENONの方はぐぐぐっと重たく力強い反動が戻ってきます。対してかめさんスピーカーは高めの周波数でびりびりする感じで力強さはありません。 これが両者の差になっているんじゃないか……という方向で考えてみました。 周波数特性とは別に、箱が持つエネルギー感みたいなものが違うんじゃないか? 色々試した結果、箱の下に自転車用のゴムチューブの切れ端を挟むと、調度良い弾力でぐぐぐっという反動になることがわかりました。切れ端は三枚重ねにして使っています。 音の方も全体的に重心が下がった感じで、ベースの音はしっかり。声もやわらかくなってうるさい感じが減った気がしました。 今までゴムは音がぶよぶよしてダメだと思い込んでいたんですが、結構良いですね。 |
 箱の鳴り方が変わったので、ダクトの方もいじってみました。 箱の鳴り方が変わったので、ダクトの方もいじってみました。まず中に貼っていたマスキングテープは、板がびりびりしなくなったので剥がしました。これで完全に吸音材ゼロです。 それから少しでも低音を出したくて、紙を薄く使ったり、ダクトを短めにしていた部分も変えておきました。 紙の薄い部分は割りばしで補強。ダクトはさらに2cmほど延長しました。 ダクトの設定は35Hzくらいで、かなり低めになっています。 ゴムで低音の力強さが出ているので、バスレフの音はあまり出さない方が、解像度が上がって聞こえる気がしました。 見た目がちょっと悪くなってしまったので、そのうちきれいに作り直したいですね。 さて、改めてメインとサブのスピーカーを聞き比べてみました。 ぱっと聞いた感じではどちらも似た系統の音で、メインのかめさんスピーカーの方が上位機種といった感じ。 DENONの方は最初はこもった音に聞こえるんですが、しばらく聞いていると低音のごりごり感が楽しくなってきます。 やはり一長一短ですが、総合力ではかめさんスピーカーでしょうか。 |
 やっぱり箱の下のゴムは外すことにしました。 やっぱり箱の下のゴムは外すことにしました。その代わり底板の真ん中あたりに、本、タオル、ゴムシートの順で重ねて押し込んでおきました。 タオルの膨らむ力で、底板と土台の間で軽く突っ張る感じになっています。 ゴム無しのインシュレーターでしっかりと箱を支えつつ、振動は適度に土台へ逃がしてやろうという狙いです。 土台の板が薄くて鳴りやすかったので、その補強にもなっているんじゃないかと思います。 |
 前回の折り曲げダクトをきれいに作り直してみたのですが、音が同じすぎてつまらなかったので、また色々と試行錯誤してみました。 前回の折り曲げダクトをきれいに作り直してみたのですが、音が同じすぎてつまらなかったので、また色々と試行錯誤してみました。その結果また一周して、元のシンプルな紙製のフタに戻ってしまいました。 紙は木工用ボンドを両面に塗って鳴き止め。さらに「コの字」型にスリットを入れて、内圧を逃がすようにしてみました。 「コの字」の縦棒の部分は上下に大きく動けるので、今までよりも内圧に強くなっていると思います。 仕組みとしては板厚分のダクトを、紙でダンプしただけと言えそうです。 それからダクトが変わって箱の中の音漏れが多くなったので、また吸音材を入れておきました。 素材は普通のタオルで、16cm×20cmくらいの量を底に敷いて使っています。 このタオルは、吸音材として最近気に入って使っている素材です。さわり心地も良いし、吸音材として見た場合、構造も非常に凝っていて良いのです。 |
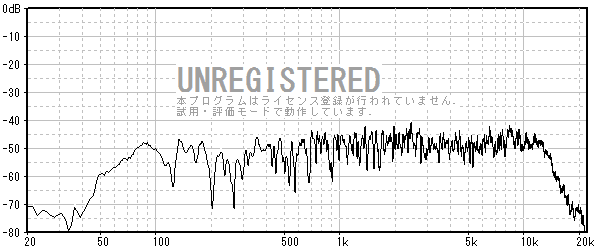 (↑カーソルを乗せると、比較用にひとつ前のグラフが表示されます) 特性を測ってみました。 前回と比べると低音がすっぱり消えてしまったようにも見えますが、聴感上は量もキレも良く、レンジも広くなっているんじゃないかと感じるくらいです。 DENONのサブスピーカーに引き続き、ようやくこちらも楽しく聞ける低音になって来ました。 |
 DENONのサブスピーカーと比べるとやっぱりダメでした。 DENONのサブスピーカーと比べるとやっぱりダメでした。どうやら100〜300Hzあたりがしっかり出ているかどうかがポイントな気がします。 逆に100Hzから下はそんなに出ていなくても良さそうな感じです。 あらためてシミュレーションしてみると、100〜300Hzあたりの音は箱を小さくした方が出しやすいようでした。 前回の試みは、穴を大きくしてバスレフの共振で無理矢理そのあたりを出そうとしたものですが、やはりバスレフでそこを出しても不自然な音になってしまいます。 大は小を兼ねるで適当に決めてしまいましたが、やっぱり箱の大きさは大事ですね。 メーカー製の箱がどれも似たような小型ブックシェルフになっているのも、ちゃんと理由があってそうなっているみたいです。 というわけで、100〜300Hzを持ち上げようと他にも色々試したのですが、うまい方法は見つからず。仕方ないので全体のバランスを整えて、相対的に100〜300Hzが聞こえやすいようにしたいと思います。 まずダクトは普通のダクトに。直径は2.0cm、長さは1.3cm。 直径はたまたま良い低音が出ているサブに合わせて小さめにしました。 1.4cmくらいの直径でも一応バスレフの効果はあるみたいですが、なんとなく音が固い感じがしたので、ゆったり鳴らすために少し大きくしました。 ポート出口で測定したところ、バスレフの山は42Hzくらいに出ているようです。 |
 設置方法も再検討してみました。 設置方法も再検討してみました。土台を頑丈にしたらどうか? インシュレーターは? メタルラックの鳴き止めにも挑戦してみたのですが、これはちょっとやそっとの制振では効き目無し。ちゃんとしたラックを買った方が早そうです。 どれも効果は微妙で、結局一番効いたのはスピーカーを壁から離すことでした。 スピーカーを前に出すと視覚的に邪魔に感じるので、高さは少し低く。箱の下に入れていた本やタオルも外してしまいました。 それから高さが下がったので、ツイーターはほんの少し上向きの角度を付けておきました。 f特にもしっかり違いが出て、ややハイ上がりになっていたのもこれで解決。f特だけじゃなく、中域の音がごっちゃになって聞き取りづらかったのも改善しました。 DENONのスピーカーの音が良かったのは、設置場所が良かったおかげでもありそうです。 |
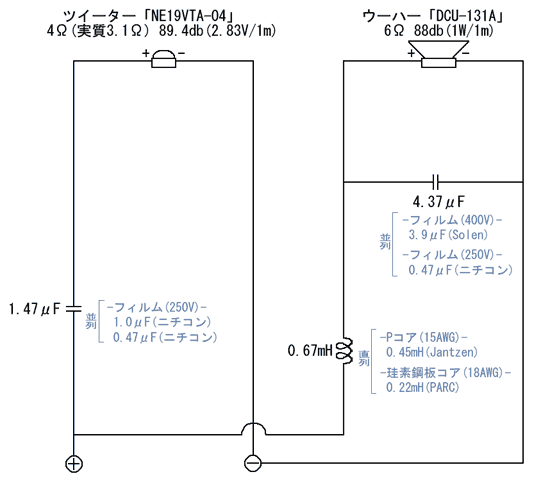 (↑カーソルを乗せると、比較用にひとつ前の状態が表示されます) ネットワークも変えてみました。 ウーハーはコイルを増やして中域の盛り上がりを防止。 ツイーターは徹底的にシンプルにしておきました。 色々と部品を買い足したのに、こんな構成になってしまって少しもったいない気もします。コイルも結局二個使いに戻ってしまいました。 |
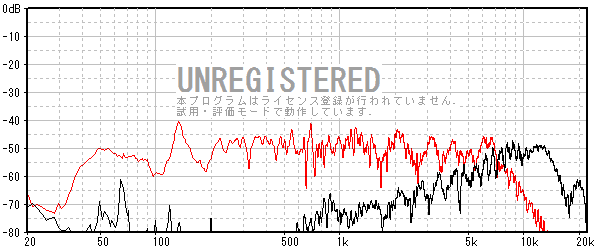 (↑カーソルを乗せると、比較用にひとつ前の状態が表示されます) クロスオーバーの具合はこんな感じになりました。 最小限の素子でも、割とうまくつながっていると思います。 抵抗をひとつも使っていないので、音も結構良いのです。 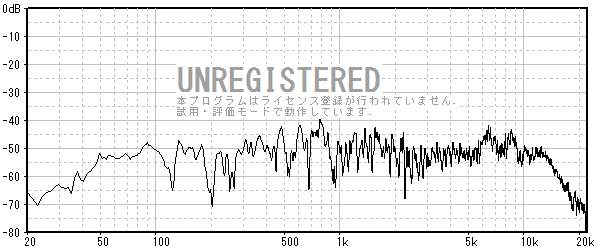 (↑カーソルを乗せると、比較用にひとつ前の状態が表示されます) Lchのみ、150cmくらい離れた普段の視聴位置での特性です。 一見デコボコの特性になってしまいましたが、ざくっと全体でとらえた時の偏りは少なくなったと思います。 音楽を鳴らした時も、バランス良く色々な音が聞こえるようになりました。 問題の100〜300Hzも大体良い感じに出ていると思います。 それから「3kHz付近がうるさい問題」も、ようやく解決できました。 ユニットの癖なのか、箱の癖なのか、フラットよりもさらに下げてやるくらいで調度良いみたいです。 |
 DENONのサブスピーカーと、もう一度比較してみました。 DENONのサブスピーカーと、もう一度比較してみました。すると今度はサブの側の低音が足りなく思えてきたので、ダクトを少し大きめに作り直しておきました。 二段階ダクトは無しにして一本のみに。直径は2.0cm、長さは5.5cmです。 さらにネットワークは、ツイーター側に1.0μFのコンデンサを1個のみに変更。 こちらもより良いバランスになったと思います。 |
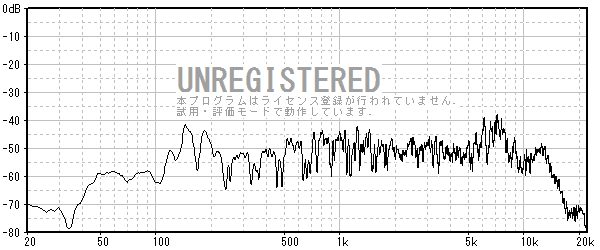 (↑カーソルを乗せると、比較用にかめさんスピーカーの特性が表示されます) サブスピーカーの視聴位置での特性です。 メインのかめさんスピーカーとは全然特性が違うのですが、ぱっと聞いた感じではどちらも似た傾向の音になっています。 100Hz以下の低音がもっと出ていると、余裕たっぷりの鳴り方になって良いのかなという感じもしますが、そのためにダクトを短くすると音が悪くなってしまうみたいでした。箱の大きさなどを考えると、このあたりがギリギリのバランスじゃないかなと思います。 しかし、これはこれでメインのスピーカーよりも切れが良く、楽しく音楽を聴かせてくれる魅力もあるので、今回はこの設定で行くことにしました。 それにしても、DENON SC-CX101に付いているウーハーは、実はすごく良いユニットじゃないかなと思います。 デフォルトの状態だと、がちがちのネットワークに抑えつけられているのが、ちょっと勿体ないくらいです。 |
だいたい良い感じの音になっていると思いますが、またどこか気になったらいじるかも知れません。 |
